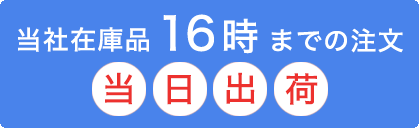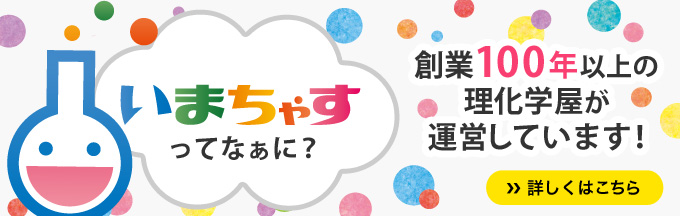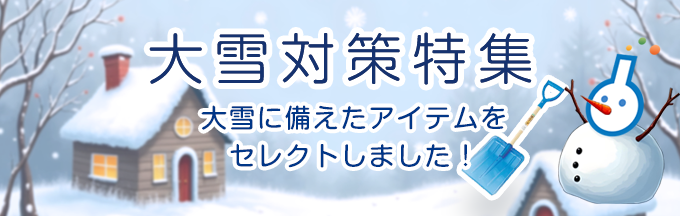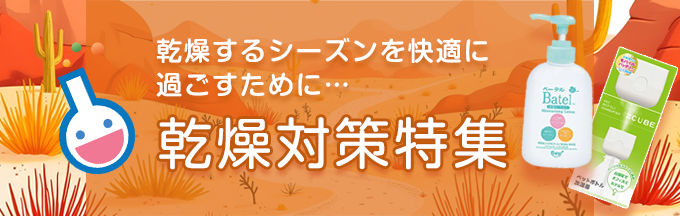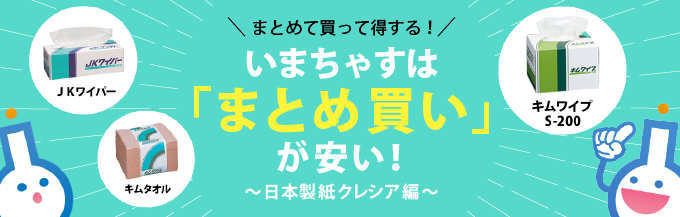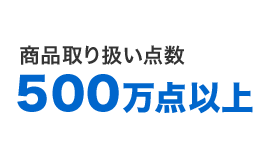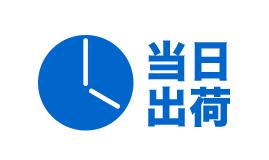なぜ標本にするの?標本の作り方は?

蝶やカブトムシなど、標本で飾られているところを見ることもあるでしょう。
この記事では、そんな標本の詳細や作り方について解説していきます。
標本とは?

「標本(ひょうほん)」と聞くと、理科室に並んでいたアルコールやホルマリン漬けの瓶、あるいは蝶やカブトムシがピンで固定された昆虫標本を思い浮かべる方も多いでしょう。
国語辞典では、標本とは「生物・鉱物などを研究資料とするために、適当な処理をして保存できるようにしたもの」と定義されています。
つまり、ただの見本や展示物ではなく学術的・教育的な目的で作られる資料なのです。
ここでいう「適当な処理」とは、対象物を長期間保存できるように工夫を施すことを指します。
例えば、動物や植物をアルコールやホルマリンに漬ける「液漬標本」、昆虫や植物を乾燥させて保存する「乾燥標本」が代表的な方法です。
その他にも、骨格だけを残した「骨格標本」や、DNAを抽出して保存する「遺伝資源標本」など、目的に応じた多様な形式があります。
標本を作る大きな目的は「研究資料」としての活用です。
動植物の形態や特徴を後世に残すことで、新しい研究や分類の基盤となり教育現場では実際に目で見て学ぶ教材として役立ちます。
また、絶滅危惧種など現存する個体数が少ない生物の場合、標本は貴重な記録として科学的にも文化的にも重要な役割を果たします。
このように、標本とは「ただ保存するためのもの」ではなく、科学研究や教育、さらには自然史を未来へ受け継ぐための大切な資料なのです。
標本の種類と役割

私たちが博物館や学校でよく目にする「標本」には、実はさまざまな種類があり、それぞれ保存方法や目的が異なります。
ここからは、そんな標本の種類について解説していきます。
剥製標本(はくせいひょうほん)
まず目を引くのが剥製標本です。
クマやトラなどがまるで生きているように保存される方法で、皮や毛を活かして外観をリアルに残すのが特徴です。
古代エジプトの時代から行われており、教育や展示の場で動物の姿を伝える重要な役割を果たしています。
骨格標本(こっかくひょうほん)
動物の骨だけを残した標本で、大型動物から小型の哺乳類まで幅広く利用される標本です。
博物館のゾウやクジラの骨格、さらに恐竜の化石展示も「骨格標本」と考えることができます。
動物の構造や進化を研究する上で欠かせません。
液浸標本(えきしんひょうほん)
アルコールやホルマリンに浸して保存する方法で、柔らかい体を持つ生物に向いています。
魚や両生類、昆虫の幼虫などは乾燥させると形が崩れてしまうため、液浸が適しています。
理科室に並んでいた瓶詰めのカエルを思い出す方も多いでしょう。
乾燥標本(かんそうひょうほん)
もっともポピュラーなのが乾燥標本です。
蝶やクワガタなどの昆虫、さらには押し花もこの方法で作られます。
比較的手軽に作成できるため、自由研究や入門用として人気の標本です。
その他の特殊標本
基本の4種類以外にも、研究や教育の現場ではさまざまな標本が利用されています。
顕微鏡観察用の「プレパラート標本」や、体内の水分や脂肪を樹脂に置き換えて保存する「プラスティネーション標本」などはその代表例です。
医療や生物学の発展に大きく貢献してきました。
標本の作り方

ここからは、数ある標本の中でも昆虫標本の作り方について解説していきます。
標本作成の注意点
昆虫標本を作るときに一番大切なのは、見た目のきれいさよりも 「しっかり乾燥させること」 です。
どんなに形を整えても、乾燥が不十分だと腐ったりカビたりして、せっかくの標本がすぐにダメになってしまいます。
昔は「昆虫採集セット」が売られており、注射器や殺虫剤などが入っていましたが実際には必要ありません。
むしろ水分を含ませてしまうと腐敗の原因になり、強い臭いを放つこともあります。
標本を長持ちさせるためには、できるだけ水分を与えないことが基本です。
昆虫を安楽死する方法(人道的で安全なやり方)
標本を作るには、まず採集した昆虫を安楽死させる必要があります。
もっとも簡単で安全な方法は「冷凍法」です。
・小さなビニール袋に昆虫を入れる
・採集場所・日付・採集者の名前を袋に書く
・タッパーに袋ごと入れ、冷凍庫で1〜2日凍らせる
これで昆虫は苦しまずに死に、標本作りに適した状態になります。
針を刺して固定する
冷凍した昆虫を室温に戻し、柔らかくなったら「昆虫針」を使って固定します。
※普通の画鋲や文房具の針では短くて扱いにくく、標本を壊しやすいので注意です。
理科教材店で専用の針を用意しましょう。
針を刺す位置は昆虫の種類によって異なりますが、基本は胸部の中央あたりです。
針をまっすぐ刺すことで展示しやすくなり、長期保存にも向きます。
標本には必ず「ラベル(採集日・場所・採集者)」を添えておくと研究資料としての価値も高まります。
乾燥と保存
針を刺した昆虫は、すぐに乾燥箱へ入れてください。
ダンボールや洋服箱を利用してもよく、その周囲に防虫剤を入れておくと害虫による食害を防げます。
乾燥はじっくり行うのが大切で、クーラーの効いた湿気の少ない部屋なら理想的です。
1か月ほど乾燥させれば、長持ちする標本になります。
仕上げとしては、専用の「標本箱」に収納するのがベストです。
しっかりした箱に入れることで、長期間にわたり保存できます。
まとめ

標本には「剥製・骨格・液浸・乾燥」といった代表的な種類があり、対象や目的に応じて使い分けられています。
さらに特殊な保存技術も発展しており、標本は単なる展示物ではなく、学術研究や教育における大切な資料と言えるでしょう。
おすすめの標本関連製品