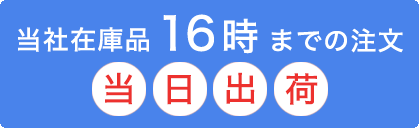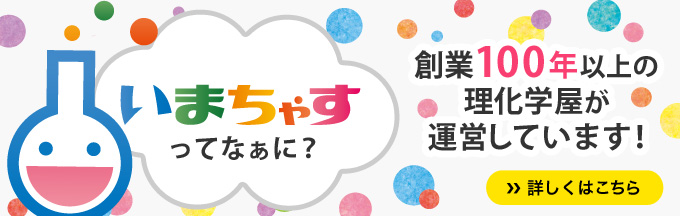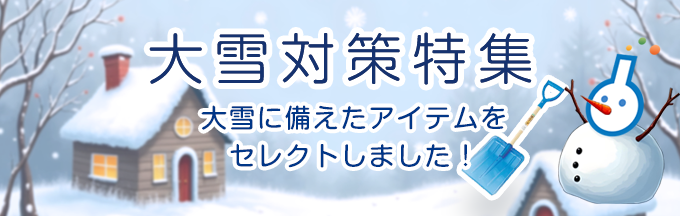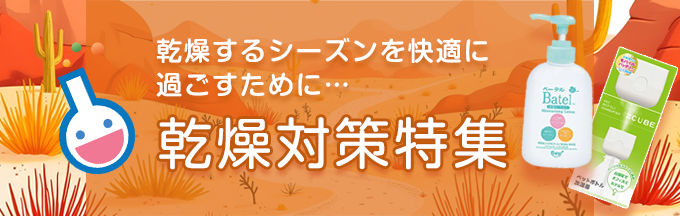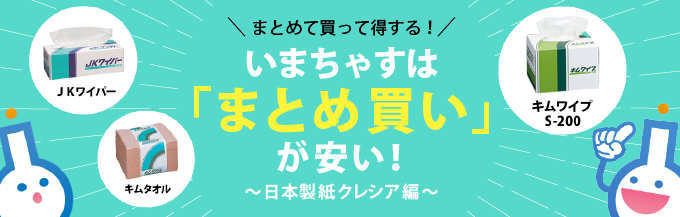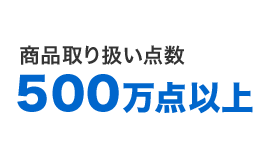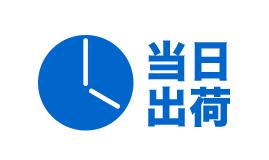介護施設での感染症対策はどうする?

介護施設での感染症の広がりは、一歩間違えると取り返しのつかないことになってしまうでしょう。
この記事では、そんな介護施設での感染症対策について解説していきます。
感染症対策が必要な理由

介護施設では、高齢で免疫力が低下している方々が多く暮らしています。
風邪やインフルエンザなどの一般的な感染症であっても、重症化や肺炎を引き起こすリスクが高く、時には命に関わるケースも少なくありません。
さらに、介助や見守りなど身体的接触が多く発生する環境では、一人が感染するとあっという間に集団感染が広がってしまう恐れがあります。
こうした背景から、介護施設では日常的かつ継続的な感染対策が必須です。
感染症対策は単なるルールではなく、「利用者の命を守る」という強い使命感のもとに行うべき行動です。
施設全体で意識を高め、誰もが主体的に取り組む姿勢が求められます。
感染経路は4つ。すべてに対応を

感染症の主な感染経路は、「接触感染」「飛沫感染」「空気感染」「血液媒介感染」の4つとなります。
例えば、手すりやドアノブなどを介する接触感染では、手洗いや手袋の着用が効果的です。
飛沫感染は会話や咳、くしゃみなどから発生するため、マスクの着用や距離の確保が有効です。
空気感染に対しては、定期的な換気が重要ですし血液媒介感染は介助中の傷口や体液に注意し、適切な防護具を使用する必要があります。
それぞれの感染経路に応じた対策を理解し、複数の予防策を重ねる「多層防御」が感染症対策の基本です。
現場の状況や利用者の状態に応じて、柔軟に対応していきましょう。
施設の出入口で“持ち込まない”対策を

感染症対策の第一歩は、外部からウイルスを「持ち込まない」ことです。
そのためには、施設の出入口での水際対策が非常に重要です。
手指のアルコール消毒、検温、マスク着用をすべての来訪者・職員に徹底しましょう。
訪問前には事前連絡をもらい、体調チェックシートへの記入をお願いすることで、万が一の感染経路の特定や連絡がスムーズになります。
職員も作業着は施設内で着用し、通勤は私服で行うなど外部との接触面を分ける工夫が必要です。
こうしたルールは明文化し、入口付近に掲示して「見える化」することで誰が見ても分かりやすく、実践しやすくなります。
出入口は感染を防ぐ最前線なのです。
事務所・会議室も油断しない

感染対策は利用者との接点だけに限りません。
職員同士が過ごす事務所や会議室でも、感染のリスクは常に存在しています。
人数制限を設ける、座席の間隔を十分に確保する、窓を開けて定期的に換気するなどの工夫が必要です。
電話やパソコン、筆記具など複数人で使用する物品の消毒も忘れてはいけません。
裏方の空間ほど油断しやすいためルールを定め、職員全員が同じ意識で行動することが重要です。
介助時は「1ケア1手洗い」が基本

食事、排泄、入浴など身体に直接触れる介助は感染リスクが高い場面です。
特に口腔ケアでは、利用者がむせることにより飛沫が広がりやすく、感染のリスクが一層高まります。
そのため、介助のたびに手洗いや手袋の交換を行い、必要に応じてフェイスガードやマスクを併用しましょう。
食事介助の際は、飛沫の影響を最小限に抑えるために斜め後方から介助する姿勢も有効です。
「1ケア1手洗い」を徹底し、毎回の介助を丁寧に行うことが施設全体の感染リスクを下げる大きな力になります。
日々の小さな積み重ねこそが、安全・安心なケアにつながります。
排泄介助・汚物処理での注意点

排泄介助や汚物処理は、感染症対策の中でも特に注意が必要な場面です。
排泄物には多くの病原体が含まれていることがあるため、処理中は必ず手袋とエプロンを着用しましょう。
処理が終わったら使い捨ての物品はすぐに廃棄し、手袋やエプロンも毎回交換が必要です。
便器の水を流す際にはフタを閉めてから行い、飛沫の拡散を防ぎましょう。
トイレや手すり、レバーといった接触が多い部分の定期清掃も重要です。
また、清掃後は必ず手洗い・消毒を行い、感染の連鎖を断ち切ることが求められます。
処理方法をマニュアル化し、誰が行っても同じ対応ができる体制を整えることが、施設全体の安全につながるでしょう。
洗濯時の“見えないリスク”に注意

衣類や寝具には、目には見えないウイルスや菌が付着している可能性があります。
洗濯作業を行う際は、手袋・マスク・エプロンの着用を徹底し、できれば汚れたリネンを仕分ける前に熱湯や消毒剤でプレ処理を行うと効果的です。
さらに、清潔な衣類と汚染された衣類が交差しないように、洗濯室の動線を一方通行にすることも重要です。
乾燥機のフィルター掃除や洗濯機の定期清掃も忘れずに行いましょう。
洗濯は見えにくい業務でありながら、感染予防の要です。
リスクを正しく理解し、慎重に行動することで職員と利用者の双方を守ることができます。
まとめ 対策は続けることが重要

感染症対策は、短期間で終わるものではなく日々の生活に根づかせる必要があります。
そのためには、職員同士が声をかけ合い、良い事例や工夫を積極的に共有できる雰囲気づくりが大切です。
「手洗いチェックリスト」や「対策カレンダー」など、視覚的に分かりやすいツールの活用も有効です。
また、「忙しいから今日は省略してしまった」という小さな油断が、大きな感染につながることを常に意識しましょう。
全員が感染対策を“自分ごと”として捉え、日々の業務に落とし込むことが利用者の命を守る強固な仕組みづくりにつながります。
おすすめの介護施設感染対策グッズ